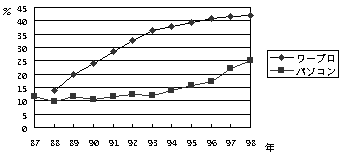|
|
|
|
* 平成11年度埼玉大学教育学部研究生(埼玉県立和光養護学校) ** 埼玉大学教育学部障害児教育講座 |
|
キーワード: 肢体障害者教育、肢体不自由児教育、コンピュータ利用、情報ネットワーク、重度知的障害者 |
1 問題と目的
技術の進展に伴って障害者とコンピュータのつながりはますます深まってきている。 電子化された情報は障害に応じて音声や点字などさまざまな形に加工しやすい。また、書字が困難な人であってもさまざまな入力装置の助けをかりれば情報を発信できる。障害者にとってコンピュータは情報の普遍性を保障する媒体としての役割を期待されている。 障害者教育の分野でも、障害を補って、コミュニケーションや学習を支援する機器として利用されている。 肢体障害者教育では、表現手段を補う目的で導入された文字盤、電動タイプライタやワープロ専用機にかわって、比較的早くからコンピュータが使われている。松本(1994)は、肢体不自由児教育(注. 本稿でいう肢体障害者教育を指す)におけるコンピュータ利用の研究動向を、電動タイプライタ、ワードプロセッサ、コミュニケーション・エイド、そしてコンピュータなどの表現手段に関する研究を背景として、その発展的な展開としてとらえることができるとしてその研究を概観している。 最近、学習の普遍性を保障するために、リハビリテーションや福祉の分野での研究成果を取り入れて、個々の障害の状況にあわせた入出力装置・ソフトウェア、入力方法を利用した事例研究などたくさん報告されるようになった。 文部省の調査(1998年3月31日現在)によれば、養護学校に置けるコンピュータの設置状況は98.4%、設置平均台数は9.7台で、ほとんどの養護学校にコンピュータが設置されている(表1)。
表1 特殊教育諸学校におけるコンピュータの設置状況(1998.3.31現在,文部省)
注. 各欄の上段の数値は、前年度の数値を表す。
詫間・成田・中村・棟方(1995)の調査によれば、肢体不自由養護学校でのコンピュータを利用した指導を行っている学校の割合は、小学部72.3%、中学部74.3%、高等部87.6%である。
表2 特殊教育諸学校の教員の実態(1998.3.31現在,文部省)
注. 各欄の上段の数値は、前年度の数値を表す。
このように、肢体障害者教育においてコンピュータ等(パソコンをはじめとする電子情報機器)を利用して学習する有効性が指摘されているし、コンピュータも広く普及し、養護学校でのコンピュータや電子ネットワークを利用した実践はめずらしくない。しかし、文部省調査(1998年3月31日現在)によれば、養護学校の教員でコンピュータを操作できる割合は34.3%、コンピュータで指導できる教員の割合は12.1%にとどまっている(表2)。この事実が示すように、実際の利用となると、広く普及しているとは言い難い。
2 時代とともに性格を変えてきた肢体障害者のコンピュータ利用
1 コンピュータ利用が進まない要因
コンピュータといっても大型コンピュータから家庭電化製品に使われるボードマイコンまでさまざまあるが、ここでは学校でも一般的に利用されているパーソナルコンピュータ(パソコン)を中心として論を進める。 肢体障害者のコンピュータ利用の普及を妨げる要因の一つは、児童生徒および教師にとってパソコンそのものの操作が容易ではない点にある。最近ではコンピュータの性能の向上に伴ってOS(基本ソフト)が進歩したので、以前に比べると操作が容易になってきたが、まだ家庭電化製品並にはいかない。 さらに、肢体障害者向けの入出力環境の整備が十分でないという問題がある。肢体障害者がコンピュータを使うためには、障害を補うための特別な入出力機器や補助ソフトが必要になることが多い。電子工学に詳しい教員が手作りで行う場合もあるが、一般的には市販されている製品を利用する。しかし、必要に応じて障害者が気軽にパソコンを使用できるようにするためには、障害にあわせた入出力ソフト・機器が開発され一部製品化されただけでは不十分である。それらが安価に手に入る条件ができ(障害者の場合には公的保障の確立も含む)、操作を容易にして(サポート体制の確立も含む)、普及させる必要がある。 もう一つの問題は、コンピュータの道具としての「わかりにくさ」に由来する教育現場での混乱である。櫻井(1998)は、コンピュータ導入が教育現場に混乱を起こしてきたと提起した。その一因としてコンピュータ自身の「わかりにくさ」をあげ、それは道具としての性格の「わかりにくさ」に由来するとして、_専用機でないこと、_完成した技術でないこと、_コンピュータが時代とともにその性格を変えてきていること、この3点を踏まえて「わかり易さ」めざす必要性を指摘した。
2 ユーザからみた歴史的区分
肢体障害者教育にけるコンピュータ利用の問題点と今後の課題を考える上で、パソコンの歴史を振り返っておく必要があると考える。そこでは、養護学校でのパソコン利用の先駆的な実践や研究をたどるだけでなく、その背景にあった半導体技術の進展や普及状況を踏まえ、どのようにパソコンが道具としての性格を変え、福祉分野・教育分野へのエレクトロニクス技術がどう応用され、障害者のパソコン利用状況がどう進んできたのかを検証し、あわせて教育行政の動向などもみることが必要である。 オフィスや学校にパソコンが普及すると、機器の性能は向上し、価格は低下した。それが、パソコンを個人で所有する条件を作り出した。オフィスや学校での普及はユーザ層の拡大をもたらし、パソコンの家庭への普及を促進させた。さらに、電気通信事業法の改正を境にパソコンはコミュニケーションツールとして飛躍的に家庭へと普及した。 ユーザの視点からパソコンの普及状況をみたとき、新しいOSが登場し、操作性が向上したことが大きな契機となっている。ここに着目してパソコンの歴史をいくつかに時代区分することができる。具体的にはプログラム言語を使って機械ごと、業務内容ごとに専用のプログラムを作っていた時代とOSとアプリケーションソフトウエアを組み合わせて利用するようになった時代とに大別でき、後者はさらにコマンド中心のOSからマウスなどのポインティングデバイスで直接操作するOS時代、ネットワークと親和性のあるOS時代などをキーワードに時期区分することができる。
3 障害者支援に焦点を当てた時代ごとのパソコン利用の特徴
世界初のコンピュータは、大砲の弾道計算のためにアメリカ陸軍の依頼によってペンシルバニア大学で研究され、1946年に公開されたENIACであった。 日本では国家の庇護のもとに研究開発が進められ、50年代後半には国産機が稼働するようになった。 70年代に入ってもコンピュータといった場合、まだ一般には大型の計算機を指していた。会社などに、次第にオフコンあるいはミニコンが導入されるようになっていくが、特定の専門家が使用することが多く、個人が利用することはほとんどなかった。 1974年、MITSがマイコン・キット「アルテア8800」を398ドルで発売。日本では、76年にNECがTK-80というキットを発売した。しかし、これらを購入して組み立てるのはごく一部のマニアであった。
2 第1期(77年〜80年)
(1)パソコンの誕生 1977年、組み立てられたパソコンとしてApple_が発売され、世界的な大ヒットとなった。このことによりパソコンの普及が始まった(「パソコン革命の始まり」といわれている)。 (2)日本語ワードプロセッサの誕生 パソコンではないが、1978年に仮名漢字変換技術が実用化されている。最初の製品は東芝JW-10で、1978年暮れから翌年にかけて発売された。大型で、値段は630万円もした(「日本語ワープロの誕生」)。 (3)リハビリテーションエンジニアの誕生 リハビリテーションの分野では、半導体エレクトロニクス技術の進展を背景として、1975年ころからリハビリテーションエンジニアが現れ、姿勢保持椅子やコミュニケーションツール、環境制御装置など個々の障害者にあわせた開発が始まった。
3 第2期(81年〜85年) 1981年、米国のIBMが16ビットのIBM
PCを発売した。単にハードウェアが優れていたというだけでなく、PC-DOS(あるいはその後マイクロソフト社からライセンスされたMS-DOS)というOS(基本ソフト)が出荷されたことと相まって、オフィスで実用的なものとなった。それまでは機種ごとのBASIC(言語)でプログラムを書いて使うスタイルであったものが、OS上で共通のアプリケーションソフトを動かすというスタイルに変わることとなったのである。
4 第3期(86年〜90年) 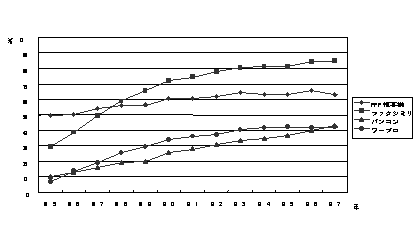
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[日本障害者協議会,「障害者のネットワークリソースBook97」(JDジャーナル号外)1997.3.(全国障害者関係BBSアンケート調査)より作成] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新しいコンピュータへの買い換えなどが進んできて、古いコンピュータを障害者や障害者を支援する団体に使ってもらおうというパソコン・リサイクル、パソコン・バンクの運動が生まれてきた。たとえば田中克典は、不用パソコンの障害者関連団体への寄贈運動を進め、報告している5)。 (4)こころリソースブックの刊行 (5)学校でのパソコン通信 (1)インターネット元年 (2)パソコンボランティア (3)情報アクセス権、情報発信権の提唱 (4)重度知的障害者へのテクノロジー活用 こうした経過を踏まえ、肢体障害者教育におけるコンピュータ利用の問題点と課題を、本稿のまとめを兼ね、6点考察し、結語としたい。 1 肢体障害者教育へのパソコンの導入と普及 (1)書字困難の補完 (2)マルチメディア化 (3)通信ネットワーク化 パソコン通信が普及すると、学校でも利用しようとする動きが現れた。障害児学校間の交流や通常の学校との交流などに利用され始めた。 (4)重度知的障害者のテクノロジー利用 2 コンピュータ導入による教育現場の混乱 コンピュータおよび「情報教育」の導入は教育現場に混乱を起こしてきた。 3 教師に求められる指導知識・技能の変化 文部省の調査によれば、養護学校において「コンピュータで指導できる教員」の割合はわずか10〜12%というのが現状である(表2)。ここでいう「コンピュータで指導できる教員」というのは、いわゆる情報教育の指導ができる教員を指すと考えられる。この統計指針に疑問がある。 4 教育的検討 (1)電子文房具としての利用 (2)情報通信ネットワークの利用 インフラを整え、情報さえ集めればいいと思っていると失敗する。櫻井(1994b)は、教育的なクローズドネットワークの必要性を指摘している。 (3)マルチメディアの利用 (4)重度知的障害者のテクノロジー利用 5 教師への支援体制 (1)教職員研修 現職教職員を対象とした研修は重要である。 (1998.3.31現在,文部省) (人) (人) (%) (人) 486 (%) (%) 4,726 1,432 30.3 590 12.5 41.2 43,307 12,263 28.3 5,551 12.8 45.3 51,388 14,646 28.5 6,627 12.9 52.2 教職員研修・教育といった場合、すぐにフォーマルな研修の充実ということを考えがちだが、パソコン操作の習得においては職場における教職員同士のインフォーマルな研修が有効であるし、重要である。そうしたことを可能にするには教職員の多忙化の解消がはかられなければならない。 (2)行政の条件整備・人的サポート (1998.3.31現在,文部省) 校 校 % 校 % 聾学校 103 103 養護学校 738 726 909 103 11.3 897 11.5 注.
各欄の上段の数値は、前年度の数値を表す。 表5に現時点での公立特殊教育諸学校のインターネットへの接続状況を示した。文部省は2001年までにすべての学校にインターネットを接続するといっているが、教師を支援する体制が整っていない現状では、安上がりで情報ネットワークを構築・管理するために、教育行政がネットワーク管理の仕事を教師に肩代わりさせてくる可能性がある。そうすると、現状では誰でもそうした仕事ができるわけではないので、特定の教員の過度の負担になりかねない。教育行政は、機器整備だけ進めるのではなく、教職員の支援についても責任を持つべきといえよう。 6 学習支援の道具へ 現状ではいろいろな場面で、いろいろな目的で、コンピュータが使われている。コンピュータは子どもが学びの主体となる学習支援の道具としての可能性を持っているといわれる(佐伯胖,1997)。事実を通して真実を学ぶための道具、学習を共有する友だちとつながるための道具にしていこうという動きも出てきている。 文 献 佐伯 胖(1997):
新・コンピュータと教育,岩波新書 櫻井宏明(1998):
「情報活用能力」とコンピュータ教育,高校のひろば,30号,34-39. 櫻井宏明(1994a):
授業でパソコンを使う,みんなのねがい,316号,18-21. 櫻井宏明(1994b):
教育実践とパソコン通信のこころみ,障害者のパソコン・ワープロ通信入門,全国障害者問題研究会出版部,56-61. 詫間晋平・成田 滋・中村 均・棟方哲弥(1995):
特殊教育における教育工学に関する調査研究(?),国立特殊教育研究所研究紀要,第22巻,37-45. 成田滋(MES)(1990):
障害児教育のためのソフトウェアとその周辺機器,アップルコンピュータ. 松本 廣(1994):
肢体不自由教育におけるコンピュータの利用,特殊教育学研究,第31巻1号,45-53. みんなのねがいネット編集委員会(1994):
障害者のパソコン・ワープロ通信入門,全国障害者問題研究会出版部. 脚 注 2)情報機器への近づきやすさ。キーボードやマウスが利用できない人たちのために、それを補助する様々な装置やソフトウェアが開発されている。 3)宇都宮敏男:
障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会・共同作業所全国連絡会・全国障害者問題研究会編(1992):
障害者の人権20の課題」,同出版部,230〜235. 4)電子掲示板(Bulletin
Board
System)のこと。これが転じてパソコン通信のことを指すようになった。 5)ここでは、不用になったパソコンを必要とする障害者団体や障害者個人に贈るリサイクル運動のこと。パソコンバンクは、不用パソコンを集めて無償で貸し出す。 6)Augmentative &
Alternative
Communicationの略。「補助代替コミュニケーション」と訳されることもあるが、AACという語がそのまま使われることの方が多い。 7)「共用品」とよばれることもある。障害者向けに特別なものを用意するということではなく、ユーザの中に障害を持つ人も含めて考える、システムや製品、機器、建造物の設計思想のこと。 8)自作スイッチで電動オモチャを動かすことなどに代表されるハイテクではないテクノロジー利用という意味。コンピュータなどのHigh
Technologyを使わない技術のこと。ローテクとも言われている。 9)こころWebは、日本において入手可能な、障害を持つ方のコミュニケーション支援機器や関連する技術情報を集めたインターネット上のWebサイト。その大部分は、香川大学教育学部中邑研究室のメンバーを始めとする、こころリソースブック編集会により編さんされた「こころリソースブック」を電子化したものである。 http://www.jeida.or.jp/document/kokoroweb/ 10)Coup de
Tech.“変革”(Coup)と“技術”(Technology)の造語。 クーデ・テック実行委員会,アップルコンピュータ,アップルディスアビリティセンター共催。協賛/協力として名を連ねているのは、日本アイ・ビー・エム、ヤノ電気、パシフィックサプライ、DON
JOHNSTON incorporation、MADENTA Communication
Inc.、アメディア、インターリンク、バンダイ、リコー、日本おもちゃ図書館財団、メディアワークス、両毛システムズ、エスビー食品、こころ工房、原宿クエスト。翌年2回目が開かれた。 11)Voice Output
Communication
Aids(音声出力コミュニケーションエイド).音声出力機能を備えたコミュニケーションエイドの総称。あらかじめ組み込まれた音声や録音しておいた音声を再生してコミュニケーションを助ける。市販されている機器では、録音できることばが1つのもの、4つのもの、12程度あるものなどいろいろなものがある。外部にスイッチをつけられるものやスキャンで選択できるものなどもある。 Physical
Disabilities School for Students with
Physical Disabilities) ** Faculty of Education,
Saitama University As computer technology advances,
five developmental steps are found in aid for QOL of persons
with handicaps in Japan. Augmentative and alternative
communication activities using computer have brought them
fruitful lives. The steps suggested also developmental
stages for teachers’
understanding of how to use computer in the treatment of
students with physical disabilities. Japanese Ministry of Education
promised to set up the Internet computer system in all
schools until 2001. This report issues it is the most
important that teachers discuss how to use successfully
computers in teaching of students with disabilities focused
on their human development and based on their human right.
That is not so important for teachers themselves to grow up
as technologists. Good teaching for students comes before
everything else. (1999.9.30 受理)
国内でもそれまでは個々のユーザにあわせて個別的にリハビリエンジニアが開発してきた機器が次第に製品化され、出回るようになってきた。入力機器などをOTやPT、教員などが自作できなくても、あるいは近くに自作できる人がいなくても、ハイテク機器を利用できる条件が生まれてきたことを意味する。決して市場の大きくない日本でもバリアフリー情報機器の開発・製造・販売を業務内容とする会社も出てきている。
パソコンがIBM
PC/AT互換機へ移行するのに対応して、こうした福祉機器もIBM
PC/AT互換機対応へとシフトしていくことになった。それまでMSXあるいはPC98シリーズ対応のものであったものがIBM互換機に移植されるようになった。たとえばスキャンで文字を選択し、意思伝達を行う装置の「漢字Pワード」もIBMのマシンに移植された(1994年4月)。
NECのPC98に代わってIBM互換機が普及し、事実上の標準となったことは悪いことばかりではなかった。日本に比べ豊富に開発され、比較的安価で販売されていた米国のIBM互換機やMacin-toshに対応した障害者向けの周辺機器やソフトウェアが利用できる条件が生まれたのだ。それまでは個人輸入などの手段で手に入れていたものが、輸入代理店が扱うようになって一般ユーザが手に入れやすくなってきたのである。
しかし、まだ、製品はあるものの、そうした製品の情報を手に入れることが容易ではなかった。そこで、中邑賢龍、太田茂、坂爪新一などが中心となって、障害者向けコミュニケーションツールの製品(フリーウェアソフトなども含む)情報を集めた「こころリソースブック」を刊行した。これにはAAC6)製品、ユニバーサルデザイン7)の製品、Simple
Technology8)の製品など幅広く紹介されている。これらの情報は後に電子化され、「こころ
Web」としてインターネット上で公開されている9)。
この時期、企業サイドでも障害者を支援するセッション設置の動きがみられる。日本IBMのSNS推進室やアップルディスアビリティセンターなどである。また、障害者と企業が中心となって、障害者が自分の障害を補うツールとしてテクノロジーを使える環境を作る目的でクーデテック(94年10月)というシンポジウムも開催された10)。
障害児教育におてもパソコン通信をどう利用するのかが模索されるようになった。視覚障害や聴覚障害の場合、パソコンを使えば、点字や手話などの特別なコミュニケーション手段を獲得してない人とも交流が可能となること、病院に入院している子どもや身体障害のために移動が制限される肢体障害者が広く社会とつながる可能性を持つことなどが期待された。商用のネットワークを利用する前段として、学校が運営するBBSを位置づけるところも出てきた。たとえば府中養護学校では、2年以上の私的試験運用を経て1992年から正式に学校としてネットワークの運用を開始している。
(6)教員の研修・研究
パソコンではないが、トーキングエイドなどのコミュニケーションエイドは学校でも広く一般的に使われるようになった。また、プログラム言語を使わなくても、比較的短時間で自主教材を作れるオーサリングツール(ハイパーカードやタウンズギア、アドベンチャーツクールなど)などが登場してきたが、教員を支援する公的な保障は少なかった。
したがって、教師が、さまざまな情報を手に入れるには、自主的な研究会に参加したり、パソコン通信の電子掲示板を利用したりすることが多かった。
この時期、教育現場では、フリーウェアの自作教材ソフトをどう作るのか、流通させるか、また入力装置や補助ソフトの紹介、Simple
Techno-logyの自作などの情報交換を問題にする段階から次第に授業や生活指導の中でパソコンをどう使っていくのかということを問題とする段階に移行しつつあった。
95年度からは毎年、MES(障害者とコンピュータ利用教育研究会)では、全国の教師が自作した教材を集めた自作教材集をCD-ROMというメディアで作成し、頒布を行うようになり、今日に至っている。
6 第5期(95年〜)
1995年はインターネット元年とよぶにふさわしい年である。1995年1月17日の阪神淡路大震災においてインターネットが注目を浴びた。被災地の映像を神戸市がインターネットを使って発信したり、インターネットなど使った情報ボランティアが活躍した。
これに先立って、WWWの代表的ブラウザソフトであったMOSAICが1994年12月にネットスケープナビゲーターとして登場していた。さらに、リムネット(プロバイダ)が、個人を対象としたインターネット接続サービスを1994年10月から開始していた。
インターネットを学校につなぐプロジェクト(「100校プロジェクト」)には、障害児学校8校が参加した。文部省はすべての学校を2002年までにインターネットに接続させる計画を表明した(後に、2001年に前倒しすると発表)。
阪神淡路大震災では全国から集まったたくさんのボランティアが活躍した。1995年はボランティア元年でもあった。
草の根BBSの多くは地域に根ざしたものである。そうした特徴を活かして、各地のBBSでは、パソコン通信のネットワークを基盤に、障害者のパソコン利用を支援する民間団体や個人レベルのさまざまなボランティア活動が生まれてきていた。日本障害者協議会(JD)では、これらを「パソコンボランティア」とよび、各地のネットワークをつないでいく構想を立て、JDのメーリングリストや商用ネットワークPeopleの福祉工作クラブなどを使ってネットワークづくりを始めた。
そうした活動を踏まえ、各地に生まれつつあったパソコンボランティア活動を交流し、障害者の情報バリアフリーに向けた課題を探るために1997年3月、第1回パソコンボランティアカンファレンスが開催された。
1995年5月、郵政省の電気通信審議会が「情報アクセス、情報発信は新たな基本的人権」と明快に打ち出した。これは、「情報にアクセスできること、情報を発信し、コミュニケーションできることは現代の新しい人権である。その権利は、知的な障害をもつ人々も含めて、すべての障害者に保障されなければならない。障害者にやさしい機器はだれもが使いやすいものである。そして、障害をもつ人に良い社会は、万人のためにも良い社会であるからである」ということが障害者関連団体の枠を超えて認められ始めたことを証明するものである。
知的障害の重い子へのテクノロジー利用(パソコンだけに限らない)の取り組みが、AACの考え方をもとに広まってきた。しかも、学校の枠にとらわれず、家庭生活なども視野に入れたSimple
Technologyを使った取り組みである。
中邑賢龍は、95年8月に香川大学で開催された第4回AACセミナーの資料として「AAC(Augmentative
& Alternative
Communica-tion)入門IIコミュニケーションでこころの自立を」を著している。
北九州市の起風会や東京のMagical Toy
Boxなどが、展示やワークショップなどのイベントを中心とした活動を始めた。いくつかの学校では、以前から取り組んできた活動を学校以外の場にも広げ始めた。
Simple
Technologyは、比較的多くの人が子どもに合わせて自作することが可能で、子どもの使用目的や教師の意図がはっきりしているものが多い。自作のよさを残している。
4 肢体障害者教育におけるコンピュータ利用の問題点と課題
特殊教育諸学校において、パソコン等の情報機器の整備は文部行政が推進してきた「情報リテラシー」という文脈の中で行われてきている。
一方、肢体不自由養護学校での実際の使われ方をみると、表現手段を補うコミュニケーションエイド的な利用が大きなウェイトを占めてきた。前述したように、学習指導要領でもこうした活用を想定している。
安価になって普及すると共に、電動タイプライタにかわってワープロ専用機が導入された。ワープロ専用機は比較的簡単に漢字を扱うことができ、入力ミスを訂正することが容易で、文章を電子情報として保存したり、受け渡しすることができるようになった。しかし、肢体障害への対応という点では多くの制約があった。
子ども一人ひとりの障害に合わせた入出力装置や入出力補助ソフトを用意すればアクセシビリティを高めることができ、しかも子どもの発達や障害の進行に合わせて対応がしやすい。情報交換の互換性が高いということもありパソコンも早くから導入されてきた。しかし、より広く普及するには、パソコンそのものの操作がやさしくなり、入出力装置や補助ソフトがより多く製品化され、特別な工学的知識を持たない教員でも指導に利用できるようになってからであろう。
はじめは主に書字の困難さを補う目的で導入されたパソコンであったが、半導体技術が進歩し、演算速度が飛躍的に向上したことによって、たくさんの量のデータを高速で処理できるようになった。それまでは扱えるデータがキャラクタ(文字)中心であったのに、音声や映像のデジタル情報を扱うことができるようになった。
また、CD-ROMドライブやDVDドライブといった大量のデータを再生する装置が普及し、学校においてもマルチメディア教材が安価に利用できる環境が整った。
インターネットを利用することで、交流はさらに広がる可能性がある。文部省は、平成10年度(1998年度)から計画的に接続を開始し、平成13年度(2001年)までに、すべての学校をインターネットに接続できるようにすると発表している。
Simple
Technologyを使ったAACなど、重度知的障害者への取り組みが本格的にはじまっている。
この場合、必ずしもパソコンではなくて、コミュニケーションボードやVOCA11)などが使用されることが多いのだが、テクノロジー利用という点では共通点がある。
パソコンの入力機器に比べると、電子技術の知識はそれほどなくても子どもにあわせたスイッチなどが自作できるとはいえ、現在、広く普及するようになったのは市販のものが使えるような環境が整い始めたからである。
(1)「情報教育」についての混乱
文部行政は、産業界からの人材養成要求に基づいて、通常の学校においても「情報教育」の中身をCAIから情報処理技術者養成教育、そして情報リテラシー教育へと変えてきた。その影響を受け、教育現場では「情報教育」のとらえ方に混乱がみられる。
(2)肢体障害者教育における混乱
障害を補うという意味での「養護・訓練」的利用、および通常の教育における情報教育が混在して、その教育的位置づけについて混乱を生じさせている。
(3)使用目的の混乱
現場からの要求に基づかず、行政主導で機器が導入されてきた。「導入されたのだから使わなければならない」という発想で、学習のねらいをはっきりさせるといった教育的な吟味を行わずに、市販されている学習ソフトなどを安易に授業に取り入れる傾向が一部に見られる。
かつて障害児学校の教師に入出力装置を自作することや学習ソフトウェアをコンピュータ言語でプログラミングすることが求められることもあった。
今日では、OS自身が入力補助ソフトを備えていたり、異なった入力装置が製品としてもたくさん普及してきているので、必ずしも入出力装置などを自作する工学的な技能も必要ない。予算が許せばこうしたものを利用すればよい時代となった。
また、自作ソフトウェア教材を創る場合でも、作成を支援してくれるソフトウェアがあるので、コンピュータ言語の知識は必ずしも必要とされない。
むしろ教員に必要とされるのは、教育の専門家としての力量である。教育的視点で入力機器やソフトを選び、利用することができる能力である。それらを道具として使って、いかに学習の普遍性を保障し、発達を保障するのかを構想する能力である。
といっても、コンピュータや情報ネットワークについての一定の理解がないことには、障害児教育でのコンピュータの利用のイメージさえもわかないだろう。しかし、その場合でも教師に求められるのはエンドユーザーとしての知識・技能でよい。すなわち「コンピュータを操作できる教員」を増やせばよいのであって、「コンピュータで指導できる教員」を増やさなくてもよい。
障害児教育におけパソコン利用では、単に障害を補うだけでなく、教育的普遍性の視点から、障害による学習の困難さを機器を利用することでどのように教育的に支援していくことができるのかを考える必要がある。
今や「このレベルの子どもにはこういう目的の使い方がある」と子どもの発達段階との関係で、いわばパソコンにたいして受け身的に整理する段階から、具体的な授業での活用事例を検討し、学習過程での教訓を整理、検討する段階に入ってきているのではないだろうか。
たとえば、櫻井(1994a)は、かな文字で書き言葉を獲得し、漢字獲得を課題とした段階の子どもにパソコン(ワープロ)を導入する際、通常使われているものをそのまま導入するのではなく、習った漢字だけが変換される子どもに合わせた専用の漢字変換辞書(インプットメソッドあるいはフロントエンドプロセッサとよばれている)をつくっている。また、送り仮名を学習するのであれば、送りがなも含めて単語を一括して変換する方法ではなく、漢字一つずつを順に変換していく「単漢字変換」という方法を選ぶ必要があることを指摘している。
さらに、櫻井は、文字を獲得していく段階の児童に、キーの配列や大きさ、キーの数の増減を自由に変更できる特殊なキーボードを使って、覚えたら文字のキーを増やしていき、最後には50音配列のキーボードとしてまとめていく取り組みを報告している。
教育的なねらいをもって用意された環境にあわせて、子どもが自分自身を変える過程を学習と言うこともできる。それは環境に適応するだけではいけない。自身の発達的変化を促すものでなければならない。入力環境等も含めて学習過程の教育的検討が必要である。
パソコン通信やインターネットなど情報ネットワークの利用についても、教育的検討が必要である。オンラインで、面識のない人とすぐにうちとけて話ができることは少ない。直接対面して得る情報量の方がはるかにが多い。対面することがなければ表層的なコミュニケーションしかできない。ホームページを作っても、受け手が誰かもわからないのに表現者になったとは言えないだろう。
また、情報さえ集められればよいのかというと、そうではない。情報が多すぎて、自分で考える機会が失われる弊害もある。
安易にマルチメディア教材に依存すべきではない。肢体障害があって実体験が難しいので、それに替えてバーチャルリアリティで済ましてしまおうという発想が一部にある。しかし、実体験をバーチャルリアリティで置き換えることはできない。使用にあたっては、慎重に検討すべきである。
同様に、就労についても、安易に「外出が困難だから、コンピュータを使って在宅で」という発想になってはいけない。在宅では孤立してしまうし、仕事と私生活の区別がつかないなどデメリットが大きいからである。
「重度知的障害者」とひとくちにいっても、そのことばは使う人によって大きな違いがある。そこで、慎重な検討が求められる。ユーザである子ども(者を含む)が、使用する機器について全部をわかる必要はないが、自分で機器を使っているという実感は必要と考える。
コミュニケーションの道具としてシンボルなどを使用するばあい、対象となる児童生徒は発達的に1歳半以降からといわれている。VOCAの使用などではそれ以前の可能性もあるが、まずは、道具を道具らしく使えるようになる発達年齢10ヵ月以降で使用を検討すべきであると考える。それ以前の段階では、パソコンやコミュニケーションエイドの使用が困難というだけでなく、一歳半の発達の節を越えるために重要な「三項関係の成立」を妨げかねないからである。電動おもちゃとスイッチを組み合わせて使う場合にも、「子ども−おもちゃ」だけの関係だけにせず、「子ども−おもちゃ−大人」の関係(「三項関係」)を育てるようにしたい。
パソコン操作の習得は「習うより慣れろ」といわれるように、パソコンの操作をマニュアルや解説本をはじめから読んで習得した人は稀であろう。多くの人は必要に迫られて、友人からの支援を受けながら試行錯誤しながら覚えたのではないか。パソコン操作の習得は講義形式や実技講習形式の研修にはなじまない。
文部省調査によれば、
養護学校の教員で、平成9年度までに何らかの研修を受けたことのある教員は12,263人である(表4)。これは全養護学校教員数の28.3%にあたる。同様にコンピュータを操作できる養護学校教員数(表2)に対する割合を求めると82.6%となるが、数回の研修で操作できるようになるほうが稀なので、研修経験のある教員のほとんどもインフォーマルなかたちで操作を習得していると推測される。
表4 特殊教育諸学校教員の研修経験
(A)
(B)
B/A
(C)
C/A
C/B
3,355
951
28.3
14.5
51.1
研修の機会を増やすだけでなく、内容についても改善する必要がある。フォーマルな研修の中で大きな割合を占めるのが、国及び都道府県教育委員会等の研修である(97年度文部省調査によれば66.1%)。特にこうした研修の内容の改善をはかっていくことが重要と思われる。
以前は、一般の教員を対象とした研修の中でもBASIC等を使って簡単なプログラムを組むことなども行われていた。最近は、代表的なアプリケーションソフトの使い方などが中心になっているようだ。
これからは、具体的操作技能の習得をねらいとしたものよりも、混乱している障害児教育における教育的位置づけを整理して示すなどの研修が求められているといえよう。講義や実技講習ばかりではなく、具体的教育実践を交流しあい、教育的視点から検討しあうような研修が有効となろう。
行政の責任として、特別な工学的技能を持たない教員も含めて必要に応じてコンピュータ等が活用できるようにするための条件整備が必要である。障害に応じた入出力機器の提供はもちろんのこと、学習を支援するための道具となるようなソフトウェアの開発提供も必要であろう。表5 公立特殊教育諸学校のインターネット接続状況
B/A
C/A
68
68
20
29.4
68
68
29.4
105
32
30.5
104
30.8
745
149
20.0
733
20.3
918
201
21.9
905
22.2
しかし、コンピュータを使うことが学習の目的ではない。「こういう場面では使わない」ということも含めて、「子どもの人格発達」という教育的視点から検討し直し、その使い方を実践的に検討していくことが必要である。
こうした検討を通じて、職員の合意づくりと自主的な教育課程編成づくりを進めていくことが要といえよう。
1)マイクロソフト社が提案した統一規格のパソコン。ゲームでのソフトは豊富である。日本では1983年10月に賛同各社から一斉に発売されるが、1984年のクリスマス商戦では、1983年7月から任天堂が発売していたファミリーコンピュータに圧倒される。
平成7年4月20日改訂,通商産業省告示第231号。
田中克典(1995):
けやき・ふれあい運動,埼玉の障害児教育とコンピュータ利用を考える会編,活動の記録,第1巻,90〜93.
Augmentativeという語には「拡大する」という意味があり、「補助」よりも広く解釈した方が適切だという見解からである。ジェスチャーやサインなどを含めて「音声以外を使ったコミュニケーション技法」と広く解釈される場合もあるが、エイドなどを用いることと解釈されることもある。ここでは後者を指して使っている。* Research Student,
Faculty of Education, Saitama University ( Wako